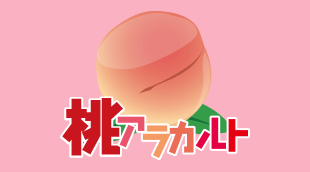- HOME
- 桃を育てよう!
- 栽培の注意点
栽培の注意点"
桃は、ほかの果物以上に傷みやすく、デリケートな果物です。
桃を自宅で栽培するときの注意点を紹介していきましょう。どんなことに気をつければいいのか分からずに、せっかくの桃は失敗に終わってしまった…なんてことのないように、注意点をしっかりチェックしておいてください。
[ スポンサードリンク ]
桃の接ぎ木
桃を連作するためには、接ぎ木をする必要があります。桃の場合は、接ぎ木の癒合が悪いので、慎重かつ、良い時期を選んでやらなければなりません。
ちなみに、桃は桃同士で接ぎ木できます。ただ、桃同士も相性の良し悪しがあるので、そのへんに注意しながら、選びましょう。
桃の接ぎ木のしかた
| 1 | 接ぎ木のための穂木を用意しましょう。2~3芽残して、少し斜めに切りましょう。 |
|---|---|
| 2 | 台木の枝を切ります。切り取った枝は、乾燥を防ぐため、少し濡らして新聞紙に包んで、ビニールで覆い、涼しいところに保管しておきましょう。 |
| 3 | 台木の樹皮にナイフで切れ目を入れます。切れ目の大きさは、穂木の太さに合わせましょう。 |
| 4 | 台木の樹皮をめくって、そこに穂木を差し込みます。そうしたら、接ぎ木用のテープで固定します。 |
| 5 | 最後に、雨や乾燥を防ぐためにビニール袋をかぶせて、接ぎ木終了です。芽が出てきたら、ビニール袋はとってくださいね。また、固定テープは次の年まで、そのままにしておきましょう。 |
桃がかかりやすい病気
桃がかかりやすい、おもな病気を紹介しましょう。いずれも、薬の散布や病気になった葉や実を取り除くことで、よくなります。
縮葉病
縮葉病の症状は、葉が火であぶったように赤く縮れてしまい、膨れ上がっていきます。それが次第に全体の葉に広がっていき、最後には枯れてしまうことがあります。
とくに春先、低い気温が続くと発病しやすいので、気をつけましょう。縮葉病の対策としては、発病した葉を摘み取って、焼却または土に埋めます。また、薬の散布も効果的です。
灰星病
灰星病の症状は、収穫時期が近くなると出てきます。桃の果実の表面に水がにじんだような斑点ができ始め、それがあっという間に広がって腐っていきます。
灰星病の対策としては、病気になった桃をそのままにしておくと、次の年の発生源をつくることになります。
なので、症状が見られる桃はもったいないですが、土の中に埋めて処分しましょう。桃に袋をかけることで、菌が入ってくるのを予防できます。
[ スポンサードリンク ]
桃につく虫
次は桃につく虫を紹介します。桃に限らず、どんな植物、果樹でも虫がつくと、とてもやっかいですよね。毎日、桃の葉や実をよくチェックしましょう。こちらも、薬の散布や虫に食べられた葉や実を取り除くことで、よくなります。
アブラムシ

アブラムシは、若葉の裏に寄生し、被害の葉は縦に巻き込みます。「アブラムシ類」の中でも特に、コフキアブラムシは、桃につきやすい虫として知られています。その名のとおり、粉をふいたように葉の裏にくっついて、葉と果実を汚してしまいます。
モモハモグリガ
モモハモグリガは葉の中に幼虫がもぐり込み、食害します。桃の葉のふちに沿って茶色くなってしまいます。さらに、葉の真ん中あたりを食べたときは、葉が丸く渦巻き状になることもあります。
シンクイムシ

シンクイムシは果実の中に入り込み、食害します。粒状のフンを果実の外に出しますが、外側は比較的きれいなため、なかなか気づきにくいですね。この虫の対策としては、薬の散布をする前に、桃に袋がけをすることで十分防ぐことができます。
[ スポンサードリンク ]