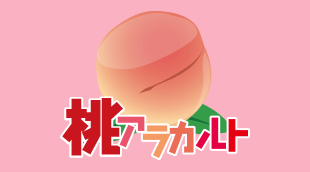- HOME
- 桃にまつわること
- 桃の節句
桃の節句
女の子のお祭りとして知られている、3月3日の「桃の節句」。
そもそも、なぜ「桃の節句」というのか、ご存じですか?一般的には「ひな祭り」といって、昔から親しまれている伝統行事と桃の関係を雑学として覚えておくといいかもしれませんよ!
[ スポンサードリンク ]
「ひな祭り」について

3月3日の「ひな祭り」は日本の伝統的な行事で、女の子の健やかな成長を祝うものですよね。一般的には「ひな人形」を飾って、桃の花や菱餅を供えてお祝いします。
このような「ひな祭り」をお祝いするようになったのは、江戸時代の中期頃からだと言われています。この頃から一般庶民のあいだで、さまざまな文化が繁栄していきました。
そんな中、「ひな祭り」も日本文化の一つとして普及していったのです。もともと「ひな祭り」の日は、赤ちゃんが初節句を迎える日にあたります。
正式には"上巳(じょうし)の節句"といって、古来中国から伝わった3月の初めの巳(み)の日という意味をもっています。ところで、"節句"という言葉…よく聞きますが、いったい何を意味しているのでしょうか?次の項目で、それを説明しますね。
五節句とは?

"節句"って、よく耳にする言葉だけど何のことなのかよく知らない…という人もいるでしょう。
"節"は、中国の暦法で定められている「季節の変わり目」のことをいいます。
昔は、奇数の数字が重なる月には、良くないことが起きると考えられていたことから、その邪気払いの意味を込めて、宴会をするようになりました。
その良くない日というのは…1月1日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日となります。
- 1月7日:人日(じんじつ)の節句
- 3月3日:上巳(じょうし)の節句
- 5月5日:端午(たんご)の節句
- 7月7日:七夕(たなばた)の節句
- 9月9日:重陽(ちょうよう)の節句
ただ、1月1日は元旦ということで特別でした。なので、1月7日を人日の節句にして、七草粥を食べることでその年の無病息災を祈ったというわけです。
[ スポンサードリンク ]
なぜ「ひな祭り」を「桃の節句」って言うの?
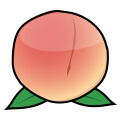
中国では古くから、"桃の木には体の中の悪いものを取り除く力がある"と考えられていました。桃に対するその考え方が日本に伝わったことで、「ひな祭り」のときに桃が使われるようになったと言われています。
また、3月上旬は、旧暦では桃の花が咲く時期とも重なります。桃の花の可憐な美しさが、女の子のイメージにつながったのではないでしょうか。
「ひな祭り」が「桃の節句」と呼ばれる理由は、ここにあったんですね!
このほか、『西遊記』に登場する孫悟空が食べたモモの話を別のページで紹介しましたが、中国で昔から信じられている仙女である、西王母(せいおうぼ)の誕生日を祝う会で食べるはずだったものを、孫悟空は食べてしまったのです…。
その西王母の誕生日というのが、3月3日になっています。
「ひな人形」の由来

昔は「桃の節句」に、草木や紙でヒトの形を作って、それで自分の体をなでて、川などに流すことで厄払いをしていました。
このときに使われたヒトの形をしたものは「人形(ひとがた)」と呼ばれ、これが現在の「ひな人形」の始まりではないかと考えられています。
また、平安時代、女の子の遊び道具として親しまれていた紙製の人形は"ひいな"と言われていました。
この"ひいな"と"ひとがた"が混ざり合い、「ひな人形」が誕生したという説もあります。江戸時代に入ると「ひな飾り」は一気に豪華になって、やがて華やかな「ひな祭り」へと発展していきました。
「ひな飾り」は、いつの時代も女の子にとって、あこがれの縮図といっていいでしょう♪
「ひな人形」は「桃の節句」に飾ることから、桃雛(ももびな)とも呼ばれているんですよ!奈良県や兵庫県、鳥取県、岡山県など、いくつかの地域では「ひな人形」を川や海に流す"流し雛"が行われています。
[ スポンサードリンク ]