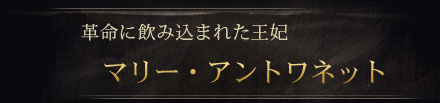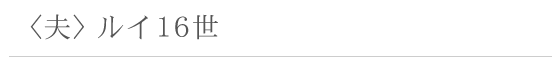| Ⅰ. | ヴェルサイユ宮殿 |
| Ⅱ. | マリー・アントワネットに 対する中傷 |
| Ⅲ. | 首飾り事件 |
| IV. | フランス革命 |
| V. | 囚われの身 |
| VI. | タンプル塔 |
| VII. | コンシェルジュリー |
| VIII. | 王妃の裁判 |
| IX. | マリー・アントワネット 最期の日 |
| 母. | マリア・テレジア |
| 夫. | ルイ16世 |
| 息子. | ルイ17世 |
| 長女. | マリー・テレーズ |
| 義妹. | エリザベート |
ルイ・オーギュスト。後のブルボン朝第5代フランス王ルイ16世です。1754年8月23日、父ルイ・フェルナンデン王太子、母、マリー=ジョセフ・ド・サクス(ポーランド王の娘)の三男として誕生しました。


ルイ・オーギュストは、ルイ15世の長男である、ルイ・フェルナンデン王太子の三男でした。
ルイ15世にとっては孫にあたります。フランスでは、王位は長子から長子へと受け継がれていく決まりになっていたので、オーギュストの兄が健在であれば、彼はフランス国王になることはありませんでした。
2番目の兄はオーギュストが生まれる前に夭逝していましたが、長兄とは一緒によく遊び、大好きで尊敬もしていました。その兄が10歳でこの世を去ります。父フェルナンデンも1765年に36歳という若さで病没し、オーギュストは11歳で王太子になりました。
ここから運命は破滅へと動いていたのかもしれません。やがて自分がルイ16世となり、国を治めていく立場だというのは自覚できていても、その行く末は、まだ誰にもわかりませんでした。





ルイ15世は若い頃は大変な美男子でとても美しい少年でした。ルイ14世の積極政策を受け継ぎ、領土を得ていましたが、財政も逼迫させていて、フランスの衰退を招いています。政治にも無関心で、寵臣ショワズールや愛妾ポンパドール伯爵夫人に政治を任せきりで、国民の不満もつのっていました。閣僚らは財政改革を何度も試みますが、その都度失敗に終わっています。
愛妾のポンパドール伯爵夫人はブルジョワ階級の娘として貴族の子女以上の教育を受けていてとても頭がよく、陰の実力者とも呼ばれたほどでしたが、42歳でこの世を去り、娼婦出身のデュ・バリー夫人が愛妾として宮廷に入ると、デュ・バリー派とショワズール派に別れて対立し、結果、ショワズールは失脚してしまいます。
のちに、ルイ16世の妃となる、マリー・アントワネットとデュ・バリー夫人も対立することになるのです。出所の悪いデュ・バリー夫人が公式寵姫として、宮廷のトップに立つほど、ルイ15世の時代の政治は乱れていたのです。
新しい王太子の見た目はあまりパッとしたものではありませんでした。何を聞いても即答することはなく、じっと考え込んでから答えるような子供でした。動作もきびきびしておらず、あまり喋らないので、周囲の人間は『おかしな子供』だと思ってしまいます。しかし、家庭教師達は王太子の才能を見抜いていました。
あまり喋らず、おとなしく、気のきいた会話もできず、優雅にダンスも踊れません。けれど、非常に飲み込みが早く、感受性も強く、頭の中は活発に動いている。そんな少年だったのです。祖父ルイ15世がなくなり、オーギュストが国王として即位したのはまだ19歳でした。妻のマリー・アントワネットはまだ18歳。若くして重責を担うことに不安を感じた2人は、抱き合って泣いたと言われています。
祖父ルイ15世とは違い、ルイ16世の治世は目を見張るものがありました。独立戦争に直面していたアメリカを積極的に援助したのは、時代の要請にこたえた外交政策と言ってもいいでしょう。今日のアメリカがあるのは、ルイ16世のお陰なのです。
1787年に寛容令を出し、それまで戸籍上の身分がなかった者にも、ちゃんと身分を認めました。信教の自由に繋がる画期的な政策です。また、水の出し入れができるドックを建設したり、刑罰の人道主義を推進し、それまで行われていた拷問を禁止しました。
地理、歴史、精密化学に精通していて、数カ国の外国語も話すことができました。不器用で優柔不断な面も持ち合わせていましたが、これまでの君主とは違い、頭脳明晰で教養の溢れる人物でした。
国王には、公妾として、公認の愛人を持つのが普通でした。数人の妾がいてもおかしくないとされていたのです。日本で言えば『甲斐性』というものでしょうか。ルイ15世には60人以上の私生児がいました。ルイ16世は優しく、包容力もあり、優れた精神的資質も持ち合わせていたのですから、女性が群がりそうなものですが、生涯マリー・アントワネットただ1人を愛していたのです。
公妾がいれば、王室に都合の悪いことも民衆は全部、公妾のせいにしてきたのですが、妾を持たないルイ16世のお陰で、全ての中傷がマリー・アントワネットに集まってしまったともいえます。どちらにせよ、フランス革命が起きるまでは、ルイ16世の国民からの評判は悪くありませんでした。
そのまま平穏な日々が続いていれば、素晴らしい国王のままでいられたのですが、ルイ15世から続く財政難に対する国民の不満に加え、マリー・アントワネットの妃としての自覚のない振る舞いに対する中傷が、フランス革命を起こしてしまったのです。
フランス革命が起こり、国王一家がタンプル塔に幽閉されてからも様々な出来事がありました。どんな出来事があっても、同様するマリー・アントワネットとは対照的に、ルイ16世は常に落ち着きをはらい、威風堂々としていました。人生の終わりが近づいてから、ルイ16世はようやくマリー・アントワネットの愛情を手に入れられたことに喜びを感じます。
これまで自分が妻に愛されていなかったこと、妻の心の中にはフェルセン伯爵がいたことを王は知っていたのです。自分がこれから断頭台に送られるというときまで、妻がこれまでの自分の行動を後悔しないだろうかと心配していました。自分が妻に対して、なんの不満も抱いていなかったという言葉を残して、ルイ16世は断頭台に身をゆだねたのです。