
『注文の多い料理店』や『銀河鉄道の夜』などで有名な文学作家、宮沢賢治と琥珀…そのあいだには、どんな関係があるのでしょうか?
この両方がイマイチ結びつかない人も多いかと思います。宮沢賢治の作品には、何度も“琥珀”の文字が登場します。彼がどれほど琥珀好きだったのかというのが作品から伺えますよ。
宮沢賢治のプロフィール
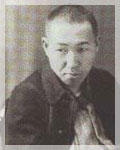 1896年、岩手県花巻市生まれ。盛岡中学、盛岡高等農林学校卒。1922年、花巻農学校教諭。
1896年、岩手県花巻市生まれ。盛岡中学、盛岡高等農林学校卒。1922年、花巻農学校教諭。
1924年、詩集『春と修羅』、童話集『注文の多い料理店』刊行。代表作は『銀河鉄道の夜』(1934年)、『雨ニモマケズ』(1931年)、『風の又三郎』(1934年)。
1926年、羅須地人協会設立。農民の生活の向上のために尽くすが、1933年、急性肺炎のため37歳で永眠。
その他・宮沢賢治に関すること
宮沢賢治は文学者であったとともに、農業指導者、教育者でもありました。今でこそ、彼の作品は世界中で愛読されていますが、生前はちっとも売れませんでした。
そんな中、以前から農業に関心を持っていた彼は、農業を通じて、自分の理想の世界を作ろうとしました。のちに、その理想郷をイーハトーヴと名付け、架空の土地として作品の中にも登場させました。
彼の永眠後、独特の世界観が多くの人々の人気を集め、世界的にも有名な作家となりました。また、教科書に載っている作品も多いため、授業で習ったこともあるでしょう。
宮沢賢治は小さな頃から石が大好きで、まわりからは「石っこ賢さん」とか「石っ子けんちゃん」などと呼ばれていました。彼は、なぜこれほどまでに石好きになったのでしょう?
彼の家のすぐそばを流れていた北上川の川原には、蛇紋岩や緑れん石、角閃石、水晶が含まれている石など、本当にたくさんの鉱物が転がっていました。これなら、子供のときから石好きになるのもうなずけます。
また、宮沢賢治は盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)で鉱物を専門に学んだこともあって、宝石や鉱物にとても詳しかったのです。宮沢賢治の文学作品には、いろんな宝石が登場します。彼はいつも、自然の作り上げた原石の美しさや、不思議な色合い、原石を磨いたときに輝き出す美しさに、感動していました。
その宝石の中の一つに琥珀があります。ほかの鉱物と同じように、川原で見つけたのでしょう。幼かった彼は、琥珀の温かな色に心を引き付けられました。そうして、短編童話『オツベルと象』や、いくつかの詩集などに琥珀という言葉を残しています。
とくに詩集では、30編もの詩の中に“琥珀”が登場します。そこで特徴的なのは、宝石の名前を書くときは必ず紅玉石(ルビー)、金剛石(ダイヤモンド)というふうに、英語名のルビをふっています。
琥珀もふつうなら「琥珀(アンバー)」となりますが、琥珀(コハク)としていました。これは、宮沢賢治が琥珀のことを岩手県の特産物として、とても身近に感じていたからだと考えられています。
ここで、宮沢賢治の文学作品や彼が詠んだ短歌の中から、琥珀に関する部分を抜粋して、紹介したいと思います。どんなところに“琥珀”という言葉が使われているのでしょう?作品から、琥珀に対する彼の愛着がうかがえます。
短編童話『オツベルと象』より
「そのうすくらい仕事場を、オツベルは、大きな琥珀のパイプをくわえ、吹殻を藁に落さないよう、眼を細くして気をつけながら、両手を背中に組みあわせて、ぶらぶら往ったり来たりする。」
童話集『注文の多い料理店の』の中の「水仙月の四日」より
「まもなく東のそらが黄ばらのやうに光り、琥珀いろにかがやき、黄金に燃えだしました。丘も野原も新しい雪でいっぱいです。」
詩集『春と修羅』より
正午の管楽よりもしげく 琥珀のかけらがそそぐとき
学生時代に宮沢賢治が詠んだ短歌より
あけがたの 琥珀のそらは 凍りしを 大とかげらの 雲はうかびて
