|
奈良・鎌倉 大仏百科 > 奈良の大仏 > 奈良の大仏の不思議
|
苦行のあらわれ |
悟りを得るためには厳しい修行が必要とされています。そのためにはどんな荒れた道でも突き進み、山を越え谷を渡り、そして大きな海原を泳ぎきらなければならないと例えられています。そこに到達することは、途中で力尽きてしまったり、おぼれてしまったりで簡単なことではないと例えられているのです。如来はこの苦行を乗り越えて、大きな海原も泳ぎきった者だということで指の間に水かきがついているとされています。 |
慈悲の心の表れ |
この水かきは「まんもうそう」と呼ばれ、水1滴も漏らさないように、人々をすくい上げるということを表現していると言われています。 |
奈良の大仏は何がきっかけで造られたのでしょうか。現在の柏原市にあった智識寺に、日本最大の大仏がありました。それを見た聖武天皇がいたく感動し、金銅の大仏を造ることを発案します。これが一般に言われている奈良の大仏が造られることとなったきっかけです。それではもう一つの怨霊鎮魂説とはどういうものなのでしょうか。
藤原四兄弟は怨霊にやられた?
天然痘の流行や干ばつ、飢饉などで荒れた世の中でした。当時の天皇家の血縁でもあった藤原四兄弟が、わずか4ヶ月のうちに、次々と天然痘で命を落とします。その頃の政権での左大臣、長屋王は安積親王に継ぐ藤原系ではない皇位継承者でした。藤原側から見ると邪魔な存在だったわけです。
このことから謀反の罪をかぶせ、長屋王を自ら命を絶つようにし向けたのが藤原兄弟でした。この藤原4兄弟が命を落としたのは、安積王や長屋王の怨霊のせいだとして、光明皇后が聖武天皇に、国分寺や東大寺、大仏の建立を勧めたのがきっかけとする説があります。
 奈良の大仏はこれまでに二度再建されてきました。現在の大仏は江戸中期、公慶という僧が再建にあたっての資金集めに奔走したのは別ページで紹介しましたが、勧心で集めた1万1000両、大阪の商人、北国屋治右衛門から銅5400キロが寄進されたほか、時の将軍、徳川綱吉とその母、桂昌院から12万1000両の援助があり、現在の大仏が造られました。
奈良の大仏はこれまでに二度再建されてきました。現在の大仏は江戸中期、公慶という僧が再建にあたっての資金集めに奔走したのは別ページで紹介しましたが、勧心で集めた1万1000両、大阪の商人、北国屋治右衛門から銅5400キロが寄進されたほか、時の将軍、徳川綱吉とその母、桂昌院から12万1000両の援助があり、現在の大仏が造られました。
7世紀に鋳造された大仏が、12世紀、16世紀、17世紀と、これまでの長い間に修復がされ、4つの時代のものがおり混ざり、言ってしまえば時代の継ぎ接ぎのようになりました。顔の色が体と違うのは、それぞれ時代が違うために色も違ってしまったのです。
奈良の大仏の完成予定日はあらかじめ決められていました。752年4月8日とされていたのです。何故だと思いますか? この日はお釈迦様が生誕した日で、日本に仏教が渡って200年目の記念すべき年でもあったのです。
実際の大仏の開眼供養会は翌日の4月9日に天皇、要人の他に、1万人もの僧が集結し、外国からの客人も大勢集まって盛大に執り行なわれました。しかし、大仏を造る場所が途中で変更になったりする中、完成したのは本体のみで、台座や大仏殿はまだ完成していなかったとされています。そこまでしても、この日に開眼供養会を行うというこだわりがあったのでしょう。
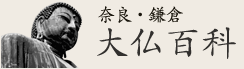

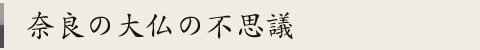
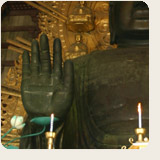 如来の手には水かきがあるのにお気づきでしょうか。もちろん奈良の大仏の手にも水かきがついています。如来三十二相の一つに挙げられ、手足指相といいます。この水かきには二つの説があります。
如来の手には水かきがあるのにお気づきでしょうか。もちろん奈良の大仏の手にも水かきがついています。如来三十二相の一つに挙げられ、手足指相といいます。この水かきには二つの説があります。