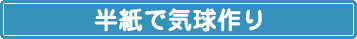たこ糸を通す穴を開ける際に、千枚通しを使います。あぶないですので、お子様ではなく、保護者の方が開けてあげるようにしてください。
- 新聞紙(しんぶんし)
- 半紙(はんし)
- 大和 (やまと)のり(『でんぷんのり』ともいいます)
- 風船(ふうせん)
- たこ糸
- 牛乳(ぎゅうにゅう)パックか紙コップ
風船(ふうせん)の大きさでどちらかをよういします。 - せんまいとおし、またはハサミ
(あぶないので、おうちの人につかってもらいましょう)
 |
 |
 |
||
新聞紙(しんぶんし)をこまかくちぎりましょう。風船(ふうせん)をふくらまして、しっかりと口のぶぶんをむすびます。 |
こまかくちぎった新聞紙(しんぶんし)を水でぬらして、風船(ふうせん)に、すきまができないように、はっていきます。 |
大和(やまと)のりを水でといておきます。 |
||
 |
 |
 |
||
風船(ふうせん)にはりつけた新聞紙(しんぶんし)が、ぜんぶかわかないうちに、水でといたのりで、半紙(はんし)を風船(ふうせん)にはります。下の新聞紙(しんぶんし)が、かくれるように、はってください。 |
しっかり、かわかしてください。かわくと、白っぽくなり、下の新聞紙(しんぶんし)もあまり見えなくなります。 |
ぜんぶかわいたら、もういちど、半紙(はんし)をはる作業(さぎょう)をします。2回くらい半紙(はんし)をはると、新聞紙(しんぶんし)が見えなくなります。 |
||
 |
 |
 |
||
しっかりかわいて、かたくなったら、風船(ふうせん)が出ているぶぶんに、セロテープをはります。 |
その上からハリ(はさみ)をさして、中の風船(ふうせん)の空気を抜いて出します。 |
気球(ききゅう)の、はじのぶぶんを、まっすぐになるように、ハサミなどでととのえましょう。 |
||
 |
||||
気球(ききゅう)ができたら、すきな絵をかいたり、おりがみをすきな形にきってはりましょう。 |
||||
気球(ききゅう)につける、ゴンドラぶぶんを作りましょう。大きな風船(ふうせん)をつかって気球(ききゅう)を作ったのでしたら、牛乳(ぎゅうにゅう)パックがいいでしょう。小さい風船(ふうせん)でしたら、紙コップをつかうと、大きさのバランスがとれます。
 |
 |
|||
紙(かみ)コップを高さ10センチくらいのところできって、はこのかたちにします。 |
紙コップに絵をかきましょう。 |
|||
いよいよ気球(ききゅう)とゴンドラをつないで、さくひんをかんせいさせましょう。気球(ききゅう)とゴンドラをつなぐたこ糸は、おなじ長さで4本ひつようです。気球(ききゅう)をつるすためのたこ糸も、きっておきましょう。
 |
 |
 |
||
気球(ききゅう)の下のぶぶん、4かしょに、たこ糸をとおすあなをあけます。 ※せんまいどおしをつかうので、おうちの人に、あけてもらいましょう。 |
気球(ききゅう)のてっぺんにも、つるすための、あなをあけましょう。 |
ゴンドラにも、気球(ききゅう)とつなぐためのあなを4かしょあけます。 |
||
 |
 |
 |
||
気球(ききゅう)のうちがわから、糸をとおして、むすびめを作ります。その上からセロテープをはっておきましょう。これで糸は、はずれてきません。 |
気球(ききゅう)の下の4かしょも、おなじように糸をとおします。 |
気球(ききゅう)につけた糸をゴンドラにもおなじようにつけます。 |
||
 |
||||
これで半紙(はんし)で作った気球(ききゅう)のできあがりです。 |
||||
もし、まだ、なつ休みやふゆ休みがのこっていたら、紙ねんどで、ゴンドラにのせる人形を作ってみましょう。人でもいいですし、どうぶつでもかわいいですね。ゴンドラにのるくらいの大きさで、絵のぐで色もぬりましょう。小さなぬいぐるみがあれば、それをゴンドラに乗せてあげてもかわいいですよ♪